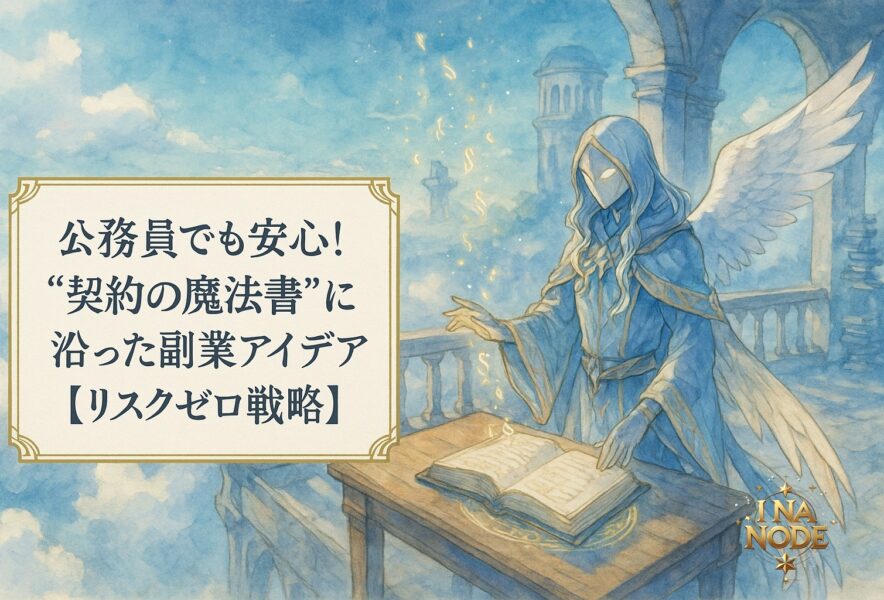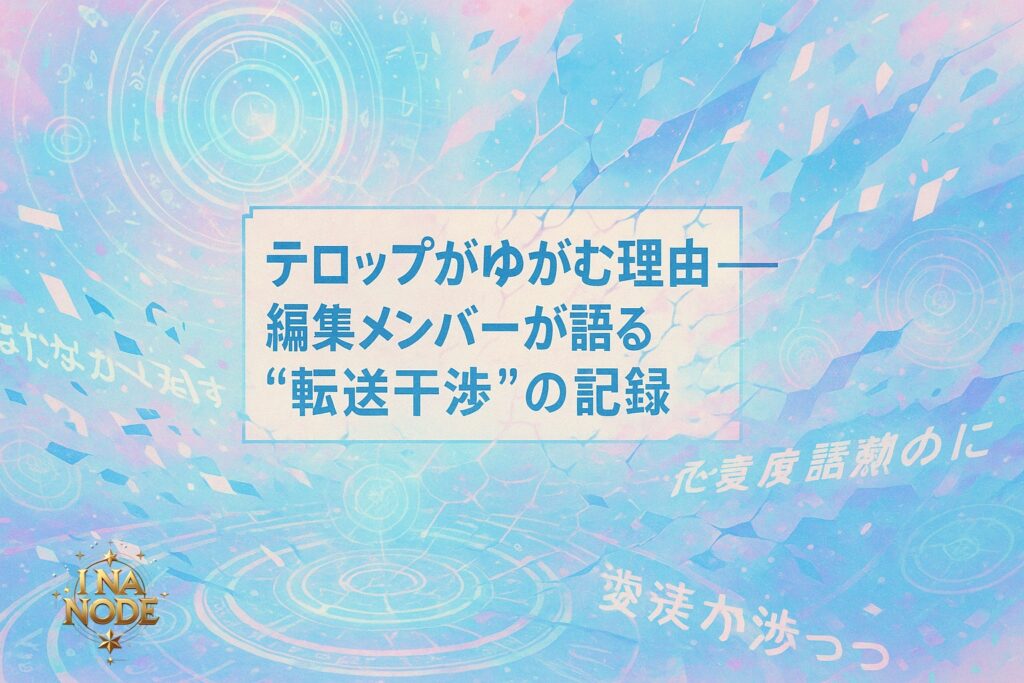副業規制と公務員の「安全圏」を見極める
公務員が副業を考えるとき、最初に向き合わなければならないのが国家公務員法・地方公務員法による兼業禁止規定だよ。一般企業では社内規定によって柔軟に認められることもあるけど、公務員の場合は法律で副業が制限されているから、無許可での兼業は懲戒処分の対象になってしまう可能性が高いんだ。
でも、ここで誤解してほしくないのは「副業は全部ダメ」というわけじゃないってこと。実は例外があって、公益性の高い活動や、許可を得た範囲内での収益活動は認められる場合があるんだ。だからこそ、「契約の魔法書」にあたる法規や通達をしっかり理解して、リスクゼロで副業を行う設計が大切になるんだよ。
たとえば次のような活動は、比較的安全圏とされやすいね。
- 作家・講師活動(業務に関連しない分野)
- 不動産賃貸(管理業務を外部委託)
- 資産運用(株式・投資信託など)
一方で、実際の行政処分の事例を調べると、「匿名であっても継続的な営利活動をしていた」ことが発覚して懲戒処分につながったケースもある。つまり副業の境界線はあいまいなようで実は明確なんだよね。


次のブロックでは、法律に沿いながら収入を得られる具体的な副業アイデアを紹介していくよ。
記録の回廊で見つけた「許可印の光」

古びた役所の地下には、外界から隔絶された「契約の魔法書保管庫」があるという。そこでは、公務員が歩んできた副業の記録が、光を放つ契約印として大切に保存されていた。
ある若い役人が、その中のひとつに手をかざすと、“趣味写真展の売上”と刻まれた印章がやわらかな光を放った。横には許可済の印が輝き、安心感を漂わせている。別の棚には“農産物の単発販売”や“地域講演会”といった安全圏の副業例が整然と並んでいた。
彼はその印の光を胸に宿し、地上に戻った。許可を得ることで、副業の道は恐れから自信へと変わる──その確信を胸に刻みながら。


副業規制と最新データの照合
総務省が公表した「地方公務員の兼業について(令和5年度)」によると、全国で許可を得た兼業件数は41,625件に上る。その内訳は「農業」「講師活動」「地域貢献活動」など、本業と無関係で公益性の高い活動が大半だ。
この数字は、公務員の副業が「法的な許可を前提とした活動」を中心としていることを示している。ただ稼ぐためだけではなく、地域や社会への貢献を重視する流れが強まっているのも読み取れるね。
📌 本業と無関係であること
📌 公益性があること
📌 事前許可または届け出を済ませていること


まとめ:契約の魔法書を味方に、副業の道を開く
公務員にとっての副業は、「やらない方が安全」ではなく「やり方次第で安全になる」ものなんだ。そのためには、契約の魔法書=法規・通達を理解し、許可や届け出を怠らないことが不可欠だよ。
安全副業は本業を守りながら収入を増やし、精神的なゆとりももたらしてくれる。たとえ小さな一歩でも、合法な積み重ねはやがて大きな可能性へと広がっていくんだ。